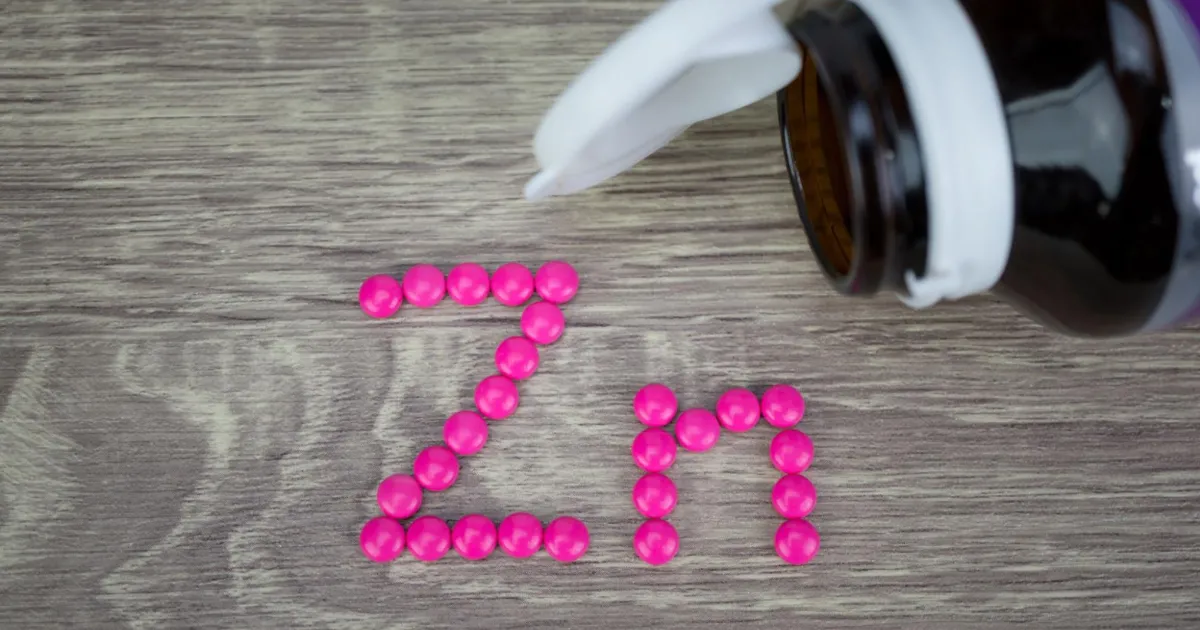亜鉛不足は、勃起力の低下に悩む男性の一因となっている可能性があります。
亜鉛は、男性ホルモンであるテストステロンの生成に不可欠な栄養素であり、不足すると性機能低下やED発症リスクの増大につながる可能性があります。
この記事では、亜鉛と勃起力の関係、亜鉛を豊富に含む食品、即効性のあるED治療薬、症状改善のための選択肢について詳しく紹介します。
食生活の改善から医療的アプローチまで、勃起力回復への総合的な対策を知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
亜鉛不足は勃起力低下の原因になるって本当?

亜鉛不足と勃起力の低下には、密接な関係があります。
亜鉛そのものが直接的に勃起力を改善するわけではありませんが、テストステロンの生成には不可欠な栄養素です。
テストステロンは男性ホルモンの主要な成分で、性欲や勃起機能に重要な役割を果たします。
亜鉛が不足すると、睾丸でのテストステロン生成が減少し、結果として男性機能の低下につながる可能性があります。
研究によると、亜鉛制限を受けた若年男性ではテストステロンが約73%減少し、逆に亜鉛を摂取した高齢男性ではテストステロン値が約2倍になったという報告があります。
このように、亜鉛の適切な摂取は、間接的に勃起力の維持や改善に影響していると考えてよいでしょう。
さらに、精子の生成や運動性にも影響を与えるため、男性の生殖機能全体に重要な役割を果たしているといえます。
亜鉛不足によって起こる勃起力低下以外の症状

亜鉛不足は勃起力の低下以外にも、さまざまな症状を引き起こす可能性があります。
日本臨床栄養学会の2018年の診療指針によると、亜鉛欠乏症の臨床症状には、皮膚炎、口内炎、脱毛症、褥瘡(難治性)、食欲低下などが挙げられています。
亜鉛は体内の300以上の酵素反応に関与しており、免疫機能、細胞分裂、タンパク質合成など、多岐にわたる生理機能に重要な役割を果たす栄養素です。
そのため、不足すると全身にさまざまな症状が現れる場合があります。
ここでは、亜鉛不足によって起こる勃起力低下以外の症状を解説します。
味覚障害
亜鉛不足による味覚障害は、食べ物の味が分からなくなったり、味を正確に感じられなくなったりする症状です。
亜鉛は味蕾の形成と機能に重要な役割を果たしており、不足すると味覚受容体の機能低下につながります。
味蕾の中には味覚センサー(味細胞)があり、味細胞の再生には亜鉛が必須です。
また、亜鉛は体内で合成したり蓄えたりができないため、食品などから摂取しなければいけません。
味覚障害は亜鉛不足の初期症状のひとつとして知られており、適切な摂取を心がければ改善が期待できるといわれています。
皮膚や爪の変形
亜鉛は、皮膚や爪の健康維持に影響している栄養素です。
不足すると、皮膚炎や脱毛、爪の変形や脆弱化が起こる可能性があります。
特に、皮膚の再生や傷の治癒には亜鉛が欠かせません。
足りていない場合は、皮膚のトラブルを引き起こしやすくなります。
例えば、蚊に刺された跡がいつまでも残ったり、化膿しやすかったりする時は亜鉛不足を疑う必要があります。
また、皮膚炎や傷を治すためにはコラーゲンというタンパク質が必要ですが、亜鉛が不足していると合成が進まないために傷の治りが遅くなります。
貧血
亜鉛不足は、貧血のリスクを高める可能性があります。
亜鉛は、赤血球の形成や成熟に必要な酵素の活性化に欠かせません。
不足していると、赤血球の生成に影響を与えます。
貧血が起こるのは、赤血球の増殖不良や膜の脆弱化によって溶血しやすくなるためです。
亜鉛は鉄の吸収や利用にも関与しているため、不足していると間接的に鉄欠乏性貧血のリスクを高める可能性があります。
鉄欠乏に合併しているケースも多く、鉄剤投与で治りにくい貧血は亜鉛不足を疑う必要があるでしょう。
下痢
亜鉛不足は消化器系の機能低下を引き起こし、下痢の原因になる可能性があります。
亜鉛は腸管の粘膜を保護し、正常な消化機能の維持を担っています。
不足すると、腸管の粘膜が脆弱になり、水分の吸収が阻害されて下痢を引き起こす可能性が高いです。
慢性的な下痢は、よく見られる亜鉛不足の症状のひとつといっても過言ではありません。
亜鉛は腸管粘膜の状態維持に働いているため、潰瘍性大腸炎や過敏性腸症候群といった診断をされている方は適切な摂取が必要といえるでしょう。
また、普段から何となくお腹の調子が悪いといったレベルの人も、亜鉛不足を疑ってみる価値があります。
免疫力の低下
亜鉛は、免疫システムを正常に機能させるために不可欠な栄養素です。
不足すると免疫細胞の生成や活性化が阻害され、全体的な免疫機能が低下します。
風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなったり、症状が長引いたりする可能性が高まります。
感染性の症状は、ウイルスを退治するTリンパ球の機能低下が原因です。
風邪をひきやすい場合は、亜鉛が足りているかチェックするとよいでしょう。
また、傷の治りが遅くなるケースも、亜鉛不足による免疫力低下の症状のひとつです。
適切な摂取ができていれば、免疫システムは正常に稼働するほか、感染症への抵抗力は弱まりません。
免疫力の低下が疑われる場合は、亜鉛不足を疑ってみましょう。
亜鉛が含まれる食品は1日にどのくらい食べればいいの?

亜鉛の1日の推奨摂取量は、年齢や性別によって異なります。
成人男性の場合は、30歳~74歳までは11mg、75歳以上は10mgとされています。
一方、成人女性は年齢に関わらず9mgが推奨です。
妊婦や授乳婦の場合は、それぞれ11mg~12mgとやや高めの摂取量が推奨されています。
子どもの場合は年齢とともに必要量が増加し、乳児では3mg程度、小児期には5〜8mg、思春期には9〜11mgです。
ただし、実際の摂取量は推奨量を下回っているケースが多く、成人男性で平均9.2mg、成人女性で平均7.7mgとされています。
亜鉛は体内で合成できないため、日々の食事から意識的に摂取すべきです。
亜鉛が含まれる食品と100gあたりの含有量は、以下を参考にしてみてください。
| 食品名 | 100gあたりの亜鉛含有量(mg) |
|---|---|
| 牡蠣 | 約13.2mg |
| 豚レバー | 約6.9mg |
| 牛肩ロース(赤肉、生) | 約5.6mg |
| 牛肩肉(赤肉、生) | 約5.7mg |
| ほたて貝(生) | 約2.7mg |
| 米飯(玄米) | 約0.8mg |
| うなぎ | 約1.4mg |
| 木綿豆腐 | 約0.6mg |
成人男性なら豚レバー、牛肩ロースや牛肩肉を約200g/日を目安にすると、必要な亜鉛を摂取できます。
参照元:公益財団法人長寿科学振興財団 | 亜鉛の働きと1日の摂取量
勃起力の低下を防ぐために摂取しておきたい亜鉛以外の栄養素

勃起力の維持には、亜鉛以外にもさまざまな栄養素を摂取しなければいけません。
血流改善、ホルモンバランスの調整、細胞の修復など、多岐にわたる機能を持つ栄養を取り込まなくては、総合的な勃起機能の向上は困難といえるでしょう。
ここでは、勃起力の低下を防ぐために摂取しておきたい栄養素をいくつか紹介します。
積極的に摂取して、勃起力の低下を予防し、健康的な性機能を維持しましょう。
ただし、過剰摂取しても即効性はないため、バランスの取れた食生活を長期的に続ける姿勢が重要です。
シルトリン
シトルリンは体内で一酸化窒素(NO)の生成を促進し、血管を拡張させる効果をもつ栄養素です。
摂取により血流が改善され、勃起力の向上をサポートしてくれます。
特徴はアルギニンの前駆体でもあり、体内でアルギニンに変換されると持続的な効果を発揮してくれる点です。
主にウリ科の植物に多く含まれており、代表的な食べ物はスイカが挙げられます。
100gあたり180mgのシトルリンが含まれており、1日の摂取目安800mgを摂るには約1/7個のスイカを食べなければいけません。
他にも、メロン(100gあたり50mg)、ヘチマ(100gあたり57mg)、冬瓜(100gあたり18mg)などにも含まれています。
これらの食品を日常的に摂取すれば、勃起機能の維持・改善を期待できるでしょう。
アルギニン
アルギニンは体内で一酸化窒素(NO)の生成を促進し、血管を拡張させる効果をもつ栄養素です。
血流が改善され、勃起力の向上を助けてくれます。
また、成長ホルモンの分泌を促進する効果もあり、全身の代謝を活性化させるのが特徴です。
主にタンパク質が豊富な食品に含まれており、代表的な食品では落花生(100gあたり3100mg)や大豆(100gあたり3000mg)、ごま(100gあたり2900mg)が挙げられます。
他にも、アーモンド(100gあたり2200mg)、エビ(100gあたり2000-2100mg)や魚介類、牛肉(100gあたり780-1300mg)、豚肉(100gあたり1300-1400mg)、鶏肉(100gあたり1200-1700mg)などの動物性タンパク質にも豊富に含まれています。
カルニチン
カルニチンは脂肪酸を細胞内のミトコンドリアに運搬する役割を果たし、エネルギー代謝を促進する栄養素です。
体内のエネルギー生産が向上し全身の代謝を活性化してくれるため、勃起力の維持や改善にも間接的に影響しています。
主に動物性食品に多く含まれ、羊肉(マトン)のロースは100gあたり約190mgと豊富です。
次いで赤貝(100gあたり108mg)、牛肉(100gあたり76-95mg)などが挙げられます。
また、豆類や牛乳にも含まれていますが、量は動物性食品と比べると少なめです。
効果的に摂取するには、マトンを中心に取り入れるといいでしょう。
ムチン
ムチンは粘液性タンパク質の一種で、体内の粘膜を保護し、潤滑作用を持つ成分として知られています。
勃起機能との直接的な関連性は明確ではありませんが、全身の粘膜健康維持に寄与するため、間接的な性機能をサポートする可能性があります。
主に動物性食品に含まれており、ナマズの皮やウナギ、フカヒレなどが挙げられます。
また、植物性食品では、オクラやナガイモ、モロヘイヤなどの粘り気のある野菜にも含まれているのが特徴です。
これらの食品を日常的に摂取すれば、性機能の健康にも寄与する可能性がありますが、断言できるレベルではないため、他に必要な栄養素との摂取を心がける程度でよいでしょう。
DHAやEPA
DHAとEPAはオメガ3系脂肪酸の一種で、血液をサラサラにする効果がある栄養素です。
血流が改善されるほか、勃起機能の維持・向上をサポートしてくれます。
また、抗炎症作用や脳機能の向上にも効果があり、全身の健康維持に欠かせません。
主に魚介類に多く含まれており、サバ、サンマ、イワシ、マグロ、ブリなどが代表的な食品です。
サバ100gあたりにはDHAが約1.3g、EPAが約0.9g含まれています。
これらの魚を週に2〜3回程度摂取すれば、十分な量のDHAとEPAを摂取できるでしょう。
魚介類以外では、亜麻仁油やエゴマ油などの植物油にもオメガ3脂肪酸が含まれていますが、含有量は魚介類に比べると少なめです。
アリシン
アリシンはニンニクに含まれる成分で、血液をサラサラにする効果がある栄養素です。
血流改善や勃起機能の維持・向上に寄与しています。
また、抗酸化作用や抗菌作用もあり、全身の健康維持にも効果があります。
アリシンは、ニンニクを切ったり潰したりすることで生成される成分です。
ニンニクを生で食べると効率よく摂取できますが、加熱調理してもある程度の効果は期待できます。
ニンニク1片(約3g)あたりの含有量は約5〜9mgです。
ニンニクは強い匂いが気になる場合もありますが、パセリやレモンと一緒に摂取すると匂いを軽減できます。
また、サプリメントで摂取すればニオイは気になりません。
ただし、食品からの摂取が最も自然で効果的です。
タウリン
タウリンはアミノ酸の一種で、体内でさまざまな重要な役割を果たす栄養素です。
血流改善や抗酸化作用、エネルギー代謝の促進などの効果があり、これらの作用を通じて勃起機能の維持・向上に寄与します。
主に動物性食品に多く含まれ、魚介類(マグロ、タコ、イカなど)や肉類(鶏肉、牛肉など)は定番です。
マグロの赤身100gあたりの含有量は、約50〜100mgといわれています。
また、エナジードリンクにもタウリンが添加されていますが、これらの飲料からの過剰摂取には注意が必要です。
タウリンは体内でも合成されますが、食事からの摂取も重要です。
バランスの取れた食事を心がけ、魚介類や肉類を適度に摂取すれば十分な量を摂取できるでしょう。
ポリフェノール
ポリフェノールは、植物に含まれる抗酸化物質の総称です。
抗酸化作用により体内の酸化ストレスを軽減し、血管の健康維持に寄与します。
主に果物や野菜、お茶、ワインなどに多く含まれ、ブルーベリーやザクロ、ブドウなどのベリー類は定番です。
他にも、緑茶やコーヒー、ココアなどの飲料、オリーブオイルなどに豊富に含まれています。
ブルーベリー100gあたりの含有量は、約300〜400mgです。
これらの食品を日常的に摂取すれば、十分なポリフェノールを摂取できます。
こんな食事には注意!勃起力が低下するリスクがあるメニュー

ここでは、勃起力が低下するリスクが上がるメニューを詳しく解説します。
ジャンクフードやスナック菓子などの高カロリーな食事
ピザ、ハンバーガー、フライドポテトなどのジャンクフードやスナック菓子は、高カロリーで栄養バランスが悪い食品です。
これらの食品は肥満や動脈硬化の原因となるほか、血流を悪化させ、勃起力の低下リスクを高める可能性があります。
また、人工的な食品添加物が含まれているケースが多く、精子の質にも悪影響を与える可能性があります。
ラーメンやインスタント食品などの塩分が高い食事
ラーメンやカップ麺などのインスタント食品は、塩分含有量が高く、勃起力の低下リスクを高める可能性があります。
過剰な塩分摂取は高血圧の原因になり、血管の健康を損なうリスクを高めます。
場合によっては勃起に必要な血流が妨げられ、勃起機能に悪影響を及ぼす可能性があります。
揚げ物やスイーツなどの脂肪分の多い食事
フライドチキンやドーナツなどの揚げ物、ケーキやチョコレートなどのスイーツは、脂肪分が多く含まれています。
これらの食品は肥満や動脈硬化の原因になるほか、血流を悪化させ、勃起力の低下リスクを高めます。
また、過剰な糖分摂取は糖尿病のリスクを高め、勃起機能に悪影響を与える可能性があるため注意が必要です。
即効性を求めるならED治療薬の服用もおすすめ!

勃起の即効性を求めるなら、食事からの亜鉛摂取でなくED治療薬の服用もおすすめです。
ここでは、特に人気の治療薬を3種類紹介します。
セルノスジェル
セルノスジェルは、テストステロンを主成分とする外用ホルモン剤です。
男性ホルモンを直接補充し、性機能の改善を図ります。
特徴は、1日1回の塗布で効果が24時間持続する点です。
勃起力の向上はもちろん、筋力アップや性機能の向上、男性更年期障害の症状緩和などの効果が期待できます。
また、飲み薬と比べて副作用が少ない点が魅力です。
ただし、前立腺疾患がある方や未成年者は使用を避けるべきです。
⇒商品リンク挿入
バイアグラ
バイアグラは、広く知られているED治療薬です。
シルデナフィルを有効成分とし、服用後30分~1時間で効果が現れ、4〜5時間持続します。
短時間での性行為を予定している場合には、効果的な医薬品といえるでしょう。
ただし、食事やアルコールの影響を受けやすいため、空腹時の服用が望ましいです。
また、強い効果を持ちますが、個人の体質や症状によっては副作用のリスクがあります。
用法・用量を守りながら適切に使用しましょう。
シアリス
シアリスは、タダラフィルを有効成分とするED治療薬です。
効果の発現は服用後1〜4時間と比較的遅いですが、持続時間は最長36時間に及びます。
長い持続時間から、ウィークエンドピルとも呼ばれるほどです。
また、食事の影響を受けにくいため、食後でも効果を発揮しやすいのがメリットです。
計画的な性生活を送りたい方や、より自然な性行為のタイミングを望む方に適しています。
⇒シアリス
まとめ
亜鉛を含む食事をバランスよく摂取すると、勃起力の維持と改善が期待できます。
亜鉛は、テストステロン生成に不可欠な栄養素です。
適切な摂取を実現できれば、勃起機能を間接的にサポートしてくれます。
牡蠣やレバー、ナッツ類、赤身肉などの亜鉛を多く含む食品を日常的に摂り入れましょう。
ただし、過剰摂取には注意が必要です。
バランスの取れた食事を心がけ、他の栄養素も適切に摂取する意識を持たなければなりません。
また、ジャンクフードや高塩分、高脂肪の食事を控え、全体的な健康維持に努めることも、勃起力の低下を防ぐうえで重要です。