ED(勃起不全)で悩む男性は世界的に見ても非常に多く、そのほとんどが身体的要因か心理的要因によって引き起こされています。
しかし、なかには「お酒」が原因で症状が現れる方も意外と多く、慢性的なEDになるケースも珍しくありません。
EDの症状で悩んでいる方のなかには、「お酒を飲むと立たない」「お酒を飲んでも立つ人はなにが違う?」と考えている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、EDの基本知識をはじめ、飲酒後にEDを発症する原因、お酒を飲んでも立つ人と立たない人の違い、立たない場合の対策などについて詳しく解説します。
ED(勃起不全)の基本知識

ED(勃起不全)は、満足な性行為を行うのに十分な勃起が得られない、または維持できない状態が持続または再発する症状を指します。
この状態は、勃起が全く起こらない場合だけではなく、硬さが不十分であったり、勃起状態を維持できなかったりする場合も含まれており、広義の概念です。
日本では、成人男性の約1,400万人がED症状を抱えているとされ、年齢とともに有病率が上昇する傾向にあります。
EDは主に加齢や心理的要因によって発症するケースがほとんどですが、お酒が原因でEDを発症するケースも少なくありません。
お酒によるEDには、一時的なものと長期的なものがあり、過度な飲酒をした場合や日常的に大量の飲酒をしている場合に発症しやすいです。
⇒ED(勃起不全)とは?発症する原因や自分で予防する方法を紹介
飲酒後にEDを発症する原因

飲酒後にEDの症状が現れるという方は少なくなく、アルコールがもたらすさまざまな作用が原因であると考えられます。
ここでは、飲酒後にEDを発症する主な原因を紹介します。
中枢神経系の抑制
アルコールが勃起機能に与える影響の主な原因の一つは、中枢神経系(CNS)の抑制作用です。
アルコールはCNSの抑制物質として作用し、脳と身体に鎮静効果をもたらします。
この作用により、脳から性器への神経信号の伝達が妨げられ、勃起の達成と維持に必要な生理学的プロセスが阻害されます。
また、アルコールは性的感度を低下させ、中枢神経系の性的興奮とオーガズムに不可欠な部分を抑制することでも知られており、ペニスの感覚が鈍くなり、通常は快感を感じる刺激がより鈍く感じられるケースも少なくありません。
さらに、アルコールの摂取量が増えるほど、認知機能への影響が大きくなるとされており、性的パフォーマンスに必要な集中力や反応時間にも影響を与える可能性があります。
ただし、個人差があり、軽度から中程度のアルコール摂取では、むしろリラックス効果によってED症状を緩和する場合もあります。
血管への影響
お酒は血管に直接的な影響を与えるため、勃起機能にも影響を及ぼす可能性が高いです。
アルコールは血管拡張作用があり、飲酒直後は血管が広がることで血流が増加します。
一時的に顔が赤くなったり、体が温かくなったりする感覚はこの作用によるものです。
適度な飲酒であれば、身体がリラックスしたり血流が良くなったりなど、プラスの効果が期待できます。
しかし、過度な飲酒は、長期的に血管系にダメージを与え、動脈硬化を進行させる可能性があります。
動脈硬化が進行すると、陰茎への血流が減少し、勃起が困難になるだけではなく、その他の疾患につながる要因となり得ます。
これらの血管への影響は、飲酒量や頻度によって異なりますが、長期的な過度の飲酒は血管の健康を損ない、結果としてEDのリスクを高めるでしょう。
適度な飲酒を心がけ、血管の健康を維持することが、勃起機能を含む全身の健康にとって重要です。
テストステロンの減少
テストステロンは男性の性機能に欠かせない重要なホルモンで、性欲や勃起機能の維持に深く関わっています。
過度な飲酒をした場合、このテストステロンの分泌に悪影響を及ぼす可能性が高いです。
アルコールの過剰摂取により、精巣の機能が低下し、テストステロンの分泌量が減少します。
長期的に過剰飲酒している場合は、テストステロンレベルが低下し、性的機能に悪影響を及ぼすかもしれません。
一方で、適度な飲酒であれば、テストステロン量を増加させる効果があるという研究結果もあります。
これは、適量のアルコール摂取が肝臓の解毒酵素の活性を上昇させ、リラックス効果をもたらすためです。
しかし、個人差も大きく、アルコールへの耐性や日頃の飲酒習慣によって、テストステロンへの影響は異なります。
健康的な性機能を維持するためには、適度な飲酒量を心がけ、テストステロンレベルに配慮することが重要です。
その他の影響(脱水症状、生活習慣病など)
お酒を飲むと、EDの原因となる血流の問題だけではなく、他にもさまざまな影響が身体に及びます。
その一つが脱水症状です。
アルコールには利尿作用があり、体内の水分を失わせる働きがあります。
これにより、血液量が減少し、血流が悪くなることでEDのリスクが高まります。
また、脱水によって体内のアンギオテンシンというホルモンの濃度が上昇し、これもEDの原因となる可能性が高いです。
さらに、長期的な過度の飲酒はさまざまな生活習慣病のリスクを高めます。
高血圧、心臓病、肝臓病、糖尿病などの慢性疾患は、血管や神経系に悪影響を与えるため、EDのリスクを増大させるかもしれません。
また、長期的な飲酒は神経系にも悪影響を与え、アルコール性ニューロパチーと呼ばれる神経障害を引き起こす可能性があります。
これは、ビタミンB群の吸収を妨げることで起こり、より永続的なEDの原因となるため、注意が必要です。
お酒を飲んでも立つ人と立たない人の違い

アルコールが与える影響は人によってさまざまであり、お酒を飲んだからといって必ずEDの症状が現れるわけではありません。
ここでは、お酒を飲んでも立つ人と立たない人の違いを紹介します。
アルコール耐性
お酒を飲んでも勃起力に影響が出にくい人と、影響を受けやすい人の違いは、主にアルコール耐性に起因します。
アルコール耐性は、遺伝的要因や飲酒習慣によって個人差があり、これが勃起力への影響の度合いを左右します。
アルコール耐性が高い人は、お酒を飲んでも中枢神経系への影響が比較的少なく、性的刺激が脳から陰茎へと正常に伝達されやすいため、勃起力が維持されやすいです。
適度な飲酒量であれば、むしろリラックス効果によって性的パフォーマンスが向上する可能性もあります。
一方で、アルコール耐性が低い人は、少量の飲酒でも中枢神経系が抑制されやすく、性的刺激の伝達が阻害されることで勃起力が低下しやすくなります。
また、アルコールの分解能力も関係しており、アルコールデヒドロゲナーゼ(ADH)やアルデヒド脱水素酵素(ALDH)の活性が低い人は、アルコールの影響をより強く受けやすいです。
健康状態
お酒を飲んでも立つ人と立たない人の違いを考えるうえで、健康状態は非常に重要な要素です。
一般的に、全体的な健康状態が良好な人ほど、アルコールの影響を受けにくく、勃起機能を維持しやすい傾向があります。
特に、心血管系の健康は勃起機能と密接に関連しています。
健康な血管系を持つ人は、アルコールを摂取しても血流が十分に保たれるため、勃起状態が維持しやすいです。
一方、高血圧や動脈硬化などの問題を抱えている人は、アルコールの影響でさらに血流が悪化し、勃起が困難になる可能性が高くなります。
さらに、全体的な体力や筋肉量も関係しています。
適度な運動習慣がある人や筋肉量が多い人は、アルコールの影響を受けにくく、勃起機能を維持しやすいです。
これは、運動が血流を改善し、テストステロン分泌を促進する効果があるためだと考えられています。
テストステロンレベル
お酒を飲んでも立つ人と立たない人の違いを理解するうえで、テストステロンレベルは重要な要因の一つです。
テストステロンは男性の主要な性ホルモンであり、性欲や勃起機能に大きな影響を与えます。
アルコールの摂取は、短期的にも長期的にもテストステロンレベルに影響を及ぼします。
少量から中程度のアルコール摂取では、一時的にテストステロンレベルが上昇する可能性があります。
しかし、過度の飲酒や長期的な大量摂取は、テストステロンレベルを大幅に低下させるリスクが高いです。
ある研究によると、アルコールを摂取してから30分以内にテストステロンレベルが約50%低下するとされており、お酒を飲んだ後に勃起が困難になる原因の一つとなっています。
一方で、テストステロンレベルが高い人や、アルコールの影響を受けにくい遺伝的要因を持つ人は、飲酒後も勃起機能を維持できる可能性が高いです。
心理的要因
お酒を飲んでも立つ人と立たない人の違いには、心理的要因が大きく関わっています。
適度な飲酒は緊張やストレスを和らげ、リラックス効果をもたらすため、むしろ勃起を促進する場合があります。
このリラックス効果により、性的な興奮が高まりやすくなる人も多いです。
一方で、過度な飲酒は中枢神経系を抑制し、性的刺激に対する反応を鈍くさせるため、勃起が困難になる可能性が高いです。
また、飲酒に対する個人の心理状態も重要な要因です。
お酒を飲むことで自信がつき、性的パフォーマンスへの不安が軽減される人もいれば、反対に飲酒によって不安が増大し、EDのリスクが高まる人もいるでしょう。
さらに、アルコールへの依存度や飲酒習慣も関係しています。
習慣的に飲酒する人は、適度な飲酒量でも勃起能力を維持できる傾向がありますが、アルコール依存症の人は長期的にEDのリスクが高まります。
お酒を飲むと立たない人ができる対策

お酒を飲むと立たないという人は、意識して対策することでEDの予防と改善を目指せる可能性があります。
ここでは、お酒を飲むと立たない人ができる対策を紹介します。
飲む量を制限・管理する
お酒は場合によっては勃起機能に悪影響を及ぼすため、飲む量を制限・管理することが重要です。
厚生労働省が推奨する1日の適度な飲酒量は、純アルコール量で20g程度とされています。
これは、ビールなら中瓶1本、日本酒なら1合、チューハイ(7%)なら350mL、ウィスキーダブルなら1杯に相当します。
自分にとっての適量を知ることも大切です。アルコール代謝には個人差があるため、自分の体質に合わせた飲酒量を把握しましょう。
飲酒量を記録し、どの程度の量で勃起に影響が出るかを観察することで、自分に適した飲酒量を見つけられるでしょう。
また、飲酒の頻度を減らすことも効果的です。
週に2〜3日は休肝日を設けることで、肝臓の健康を保ち、性機能への悪影響を軽減できます。
習慣的な飲酒は勃起力だけではなく、身体全体の健康状態にも影響するため、日頃から注意しておくことが重要です。
ゆっくり飲むように意識する
お酒を飲むと立たなくなる方でも、飲み方を工夫することで勃起力を維持できる可能性があります。
その方法の一つが、ゆっくりと飲むことです。
急激なアルコール摂取は中枢神経系に強い影響を与え、勃起機能を低下させる可能性が高くなります。
ゆっくり飲むことで、体内のアルコール濃度の急激な上昇を防ぎ、中枢神経系への影響を最小限に抑えることが可能です。
また、ゆっくり飲むことで、自分の適量を把握しやすくなり、飲みすぎを防ぐことにも役立ちます。
具体的な方法としては、一口ごとにゆっくりと味わいながら飲むこと、食事と一緒に飲むことなどです。
食事と一緒に飲むことで、アルコールの吸収速度が遅くなり、胃にとどまる時間が長くなるため、ゆっくりと吸収されるようになります。
ゆっくり飲むことで、適度な酔い心地を楽しみつつ、勃起機能への悪影響を最小限に抑えることができるでしょう。
お酒と水を交互に飲ようにする
お酒を飲むと立たなくなるという方は、お酒と水を交互に飲むよう意識してみてください。
この方法は、アルコールの摂取量を抑えつつ、体内の水分バランスを保つのに有用です。
まず、アルコールには利尿作用があるため、体内の水分を失わせる要因になります。
脱水状態になると血液の粘度が上がり、勃起に必要な血流が妨げられるため、EDの症状が現れる可能性が高まります。
水を定期的に摂取することで、この脱水状態を防ぎ、血液の循環を促進することが可能です。
また、お酒と水を交互に飲むことで、アルコールの吸収速度を遅らせることができます。
急激な酔いを防ぎ、中枢神経系への影響を軽減することで、性的興奮を脳から陰茎へと伝える神経伝達が維持され、勃起機能への悪影響を最小限に抑えることができるでしょう。
性行為前はお酒を飲まない
お酒を飲むと立たなくなる人にとって、最も効果的な対策は性行為前の飲酒を控えることです。
アルコールは中枢神経系に影響を与え、脳からの性的刺激が陰茎に伝わりにくくなるため、勃起が困難になったり、勃起力が低下したりする可能性があります。
また、アルコールには利尿作用があり、脱水状態になることで血液の循環が悪化し、勃起に必要な血流が十分に確保できなくなってしまいます。
さらに、過度な飲酒は男性ホルモンであるテストステロンの分泌を減少させ、長期的にEDのリスクを高める要因となるため、非常に危険です。
性行為を楽しみたい場合は、その日の飲酒を控えるか、少量に抑えることが賢明です。
適量の飲酒であれば、リラックス効果により心因性EDの改善につながることもあるため、自分の適量を把握し、それを超えないようにすることが重要です。
ED治療薬を使う
お酒を飲むと立たなくなる人にとって、ED治療薬の使用は効果的な対策の一つです。
バイアグラやレビトラ、シアリスなどのED治療薬は、適量のアルコールと併用しても問題ありません。
これらの薬は、勃起を促進する効果があり、アルコールによる勃起機能の低下を補うことができます。
ED治療薬のなかには、飲食の影響を受けにくいものもあり、食事やアルコールに関係なく服用できるため、お酒を飲む機会が多い方にとっては便利な選択肢となるでしょう。
ただし、ED治療薬の効果を最大限に引き出すためには、空腹時に服用するのがおすすめです。
ただし、過度な飲酒はED治療薬の効果を減少させる可能性があるため、注意が必要です。
アルコールとED治療薬を併用する場合は、普段よりも飲酒量を控えめにすると良いでしょう。
なお、ED治療薬を使用する際は、必ず医師の診断と処方を受けるようにしてください。
ED治療薬は医薬品であるため、健康状態や既往歴によっては服用できない可能性があります。
お酒を飲むと立たない人におすすめのED治療薬
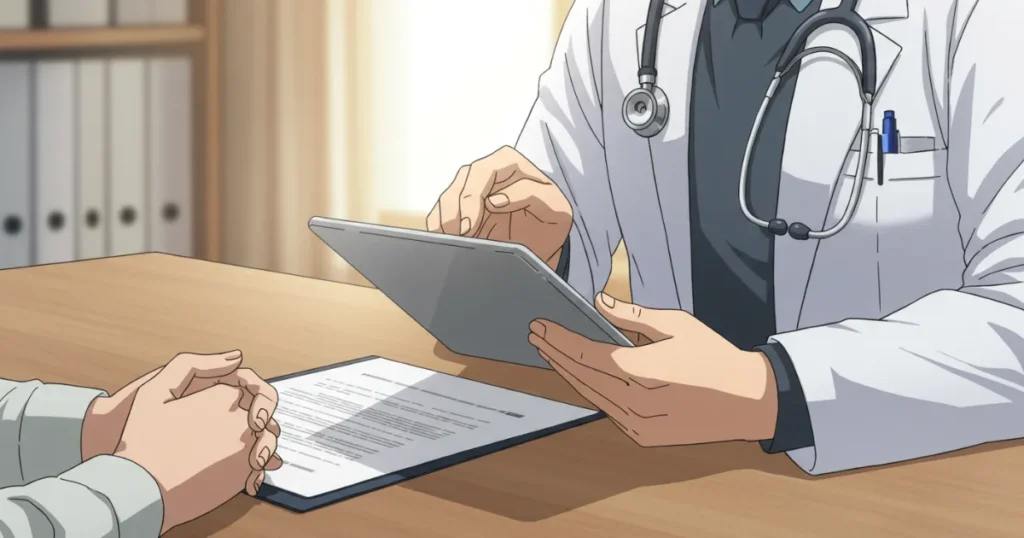
お酒を飲むと立たない人は、ED治療薬を使用することで症状が改善する可能性があります。
ここでは、数あるED治療薬のなかで特に人気が高いものを紹介します。
バイアグラ
バイアグラは、お酒を飲むと立たない人にとって有用なED治療薬の一つです。
この薬は血流を改善し、勃起を促進する作用があります。
ただし、アルコールとの併用には注意が必要です。
適度な量のアルコール(例えば、ワイン1〜2杯程度)であれば、バイアグラの効果に大きな影響はないとされています。
しかし、過度の飲酒はバイアグラの効果を減弱させ、副作用のリスクを高める可能性があるため、注意が必要です。
アルコールとバイアグラの併用で最も懸念されるのは、血圧低下のリスクです。
両者とも血管を拡張する作用があるため、同時に摂取すると急激な血圧低下を引き起こすリスクがあります。
バイアグラを服用する際は、アルコールの摂取量を控えめにしましょう。
どうしても飲酒する場合は、1〜2杯程度に抑え、自身の体調をよく観察することが大切です。
レビトラ
お酒を飲むと立たない人にとって、レビトラは非常に有効なED治療薬の選択肢の一つです。
レビトラの主成分であるバルデナフィルは、他のED治療薬と比較して飲食の影響を受けにくいという特徴があります。
これは、お酒を飲んだ後でも効果を発揮しやすいことを意味します。
レビトラは服用後15〜30分程度で効果が現れ、約5〜8時間ほど持続するため、即効性と持続性のバランスが良いです。
また、食事や飲酒の影響が少ないため、お酒を楽しみながら性行為に臨みたい方に適しています。
ただし、注意すべき点もあります。
レビトラは適量のアルコールとの併用であれば問題ありませんが、過度な飲酒は避けるべきです。
多量のアルコールを摂取すると、レビトラの血管拡張作用によってアルコールの性的興奮抑制作用が強まり、かえって勃起が困難になる可能性があります。
⇒レビトラ
シアリス
シアリスは、お酒を飲むと立たない人に適したED治療薬です。
他のED治療薬と比較して、シアリスはアルコールの影響を受けにくいという特徴があります。
そのため、適度な飲酒であれば、シアリスの効果を損なうことなく勃起を促すことが可能です。
シアリスの主成分であるタダラフィルは、血管を拡張させて陰茎への血流を改善する働きがあります。
この効果は、アルコールを摂取しても大きく変わることはありません。
むしろ、適量のアルコールは精神的な緊張を和らげる効果があるため、EDの症状緩和に役立つ場合もあります。
シアリスの効果は服用後約24〜36時間持続するため、飲酒のタイミングを考慮しやすいのも利点です。
飲酒前にシアリスを服用しておけば、お酒を楽しんだ後でも勃起機能を維持できる可能性が高くなります。
ただし、個人差があるため、自分に合った飲酒量とシアリスの服用タイミングを見つけることが重要です。
⇒シアリス
まとめ
お酒と勃起は直接的な関係はないと思われがちですが、想像以上に関係性が深いです。
アルコールが人体に与える影響は大きく、適量を超えて飲んでしまうと勃起に必要な血流やテストステロンが減少してしまいます。
一時的な飲酒であればアルコールが抜けると共に勃起力も回復する可能性があります。
しかし、習慣的な飲酒は慢性的なEDリスクを高めるため注意が必要です。
お酒を飲むと立たないという方は、お酒の飲み方を見直したりED治療薬を活用したりなど、自分に合った対策を講じてみてください。
ED治療薬は通販でも購入可能なため、自分に合う薬を把握している方や自宅にいながら手軽に入手したいと考えている方は、選択肢の一つとしてご検討ください。









